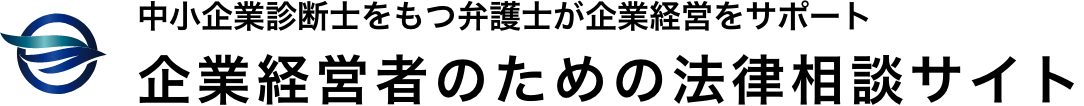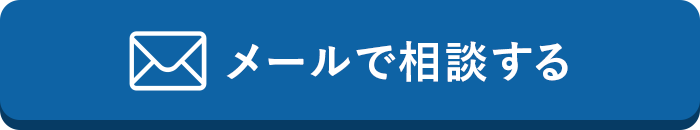緊急時に対応するために、労働者に対して休日労働を命じる場合もあります。
しかし、企業は無条件に休日労働を命じることができるわけではありません。また、休日労働を命じられた労働者には、一定程度の肉体的心理的な負担を生じさせるものですから、労働者に対する配慮も必要です。時には、休日労働を拒否されるケースもあり、企業としては、どのように対応するべきか悩ましいこともあります。
休日労働に関する悩みを抱える方は少なくありません。そこで、この記事では、企業が休日出勤を強制できるのかどうか、また従業員が拒否した場合の企業の対応について詳しく解説します。
休日出勤を強制することはできる
休日出勤を強制することは可能です。
しかし、無制限に休日労働を命令することはできません。36協定や雇用契約上の根拠などの条件を満たさなければ、企業は労働者に対して休日出勤を強制することはできません。
また、休日労働の命令ができる根拠があっても、企業は労働者の権利を尊重しなければなりません。
休日と休日労働の基本
企業が労働者に対して休日出勤を命じることができるかを検討するにあたっては、休日の意味を正確に理解しておく必要があります。
以下では、労働法における休日や休日労働の基本を解説します。
法定休日・所定休日とは
労働基準法では、労働者に毎週少なくとも1日の休日を与えることを義務付けており、この休日を法定休日と呼びます。
多くの企業では日曜日を法定休日としていますが、必ずしも日曜日である必要はありません。
一方、所定休日は法定休日以外に企業が独自に定める休日のことを指します。一般的には土曜日や祝日が所定休日となることが多いですが、企業によって異なります。
法定休日と所定休日の大きな違いは、労働した場合の割増賃金率にあります。法定休日に労働した場合は35%以上の割増賃金を支払う必要がありますが、所定休日に労働をしたとしても、休日労働には該当しないため、割増賃金は時間外労働をしない限り発生しません。
また、法定休日労働は36協定の締結が必要ですが、所定休日労働は必ずしも36協定の締結は必要ありません。
振替休日と代休とは
振替休日は、あらかじめ休日を他の労働日と入れ替えて、本来の休日に労働し、その代わりに他の労働日を休日とすることをいいます。一方、代休は、法定休日に労働させた代わりに、その代償として事後に付与する休日をいいます。
振替休日の場合、休日労働にあたらないため、割増賃金は発生しませんが、代休の場合、休日労働に当たるため割増賃金が発生します。
休日労働とは(法定休日に労働すること)
休日労働とは、労働基準法で定められた法定休日に労働者が就業することを指します。
法定休日は、使用者が1週間に1日以上または4週間に4日以上与えなければならない休日です。この法定休日に労働者が働く場合、それが休日労働となります。労働者に休日労働をさせた場合、割増賃金の支払いが義務付けられています。法定休日労働の場合、通常の賃金の35%以上の割増賃金を支払う必要があります。

休日出勤を強制するための条件
企業が労働者に対して休日出勤を強制するには、いくつかの条件を満たす必要があります。企業は、以下で紹介する、各条件を十分に考慮した上で、休日出勤の強制を検討する必要があります。
36協定があること
36協定は、労働基準法第36条に基づいて労使間で締結される協定であり、休日労働や時間外労働を可能にする重要な取り決めです。企業が従業員に休日出勤を命じるためには、この36協定が締結されていることが前提条件となります。
36協定がない場合、原則として休日労働を命じることはできません。たとえ緊急の業務があったとしても、36協定なしでの休日出勤の強制は労働基準法違反となります。そのため、企業は事前に36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ておくことが重要です。
ただし、36協定があるからといって無制限に休日出勤を命じられるわけではありません。協定で定められた範囲内であることはもちろん、業務上の必要性や労働者の個別の事情も考慮する必要があります。
休日出勤の理由・日数が36協定に違反していないこと
休日出勤を命じる際には、36協定の内容に違反していないことが重要です。36協定には、休日労働をさせる具体的な事由、業務の種類、休日労働させる日数などが定められています。企業は、この協定の範囲内で休日出勤を指示する必要があります。
企業は、休日出勤を指示する前に、36協定の内容を確認し、労働者の健康と生活に配慮しつつ、業務上の必要性と照らし合わせて判断することが求められます。協定の範囲内であっても、過度な休日労働は労働者の健康を害する可能性があるため、慎重に検討する必要があります。
就業規則・雇用契約に基づく休日出勤命令であること
休日出勤命令を出すためには、36協定だけでなく就業規則や雇用契約書に休日労働に関する規定が明記されていることが前提となります。
つまり、36協定を締結し、届出を行っても、それは、時間外労働や休日労働に対する免罰的な効果が生じるだけで、36協定だけでは休日労働を義務付ける根拠にはなりません。
そのため、休日労働を義務づけるためには、就業規則や雇用契約書で休日労働を命じることができる旨の規定があることが必要となります。
休日出勤命令に業務上の必要性があること
休日出勤命令を出す際には、業務上の必要性が不可欠です。
単なる経営者の気まぐれや、従業員への嫌がらせではなく、会社の業務遂行上、真に必要な場合にのみ認められます。例えば、納期の迫った重要プロジェクトの完了、機械の緊急修理、季節的な需要増加への対応などが該当します。
休日出勤を拒否できる場合とは
労働者に正当な理由があれば休日出勤を拒否することができます。企業側は労働者の事情を十分に考慮し、無理な休日出勤の強制は避けるべきです。
労働者は正当な理由があれば休日出勤を拒否できる
労働者は、正当な理由がある場合には、休日労働を拒否することができます。
通院や冠婚葬祭への出席、育児や介護の必要性などが正当な理由として認められます。
通院の必要がある
通院の必要がある場合、労働者は休日出勤を正当に拒否できる可能性が高くなります。定期的な通院や治療が必要な持病がある場合、その日程を変更することが困難であり、健康管理の観点からも重要です。
また、急な体調不良や怪我による通院の必要性も、休日出勤を拒否する正当な理由となり得ます。このような場合、労働者の健康と安全を優先することが求められます。
冠婚葬祭に出席する必要がある
冠婚葬祭への出席は、休日出勤を拒否する正当な理由の一つとなります。結婚式や葬儀などの重要な家族行事は、個人の生活において非常に重要な意味を持ち、社会的にも参列が求められる場合が多いためです。
育児・介護をする必要がある
育児や介護の責任を負う労働者にとって、休日出勤は特に大きな負担となる場合があります。子どもの世話や高齢の親族のケアなど、休日に果たすべき重要な役割がある場合、休日出勤の要請に応じることが困難な状況が生じやすくなります。
このような状況下では、労働者が休日出勤を拒否する正当な理由となり得ます。
私用を理由に拒否できるか?
労働者が私用で休日労働を拒否できるかは、業務上の必要性や業務命令の時期によります。
例えば、企業があらかじめ日時を指定して休日労働を指示したところ、労働者側から休日労働を拒否する申し出がされていない場合には、労働者は当日や直前になって休日労働を拒否することは原則できません。一方、休日労働を指示した直後に、労働者が正当な理由を示して休日労働を拒否する場合、休日労働の命令を撤回しなければならないこともあります。
他方で、企業が直前に休日労働を命令したところ、労働者から直ちに拒否された場合です。拒否する理由が容易に変更することのできる私用である場合には、労働者は休日労働を拒否することはできないと考えられます。
ただ、企業としては、業務上の必要性の程度と労働者の不利益の程度を比較した上で、労働者の私生活上の自由を尊重するために休日労働命令を撤回することもあるでしょう。
有給休暇の取得を認めるべきか?
休日労働を命令したところ、労働者から有給休暇の申請を受けた場合、企業はこれを認めるべきか問題となります。
そもそも、休日労働とは、労働義務のない休日に仕事をすることをいいます。休日労働をさせても、休日が労働日になるわけではありません。他方で、年次有給休暇は、賃金を減らすことなく所定労働日に休養させるために付与されるものです。つまり、有給休暇の対象は労働日であることが必要となります。
したがって、休日労働を指示した日を対象に年休を請求されても、企業は年休を与える必要はありません。
休日出勤を命令した場合の注意点
休日出勤を命令する際には、企業側が注意すべき重要なポイントがいくつかあります。
休日出勤を命じる際は、36協定の内容を遵守し、就業規則や雇用契約に基づいた適切な手続きを踏むことを忘れてはいけません。労働者の権利を尊重しつつ、企業の業務遂行に必要な人員を確保するバランスを取ることが、円滑な労使関係を維持する上で重要です。
休日労働割増賃金を支払う
休日労働に対しては、通常の労働時間の賃金に加えて割増賃金を支払う必要があります。
法定休日労働の場合、少なくとも35%の割増率で計算した賃金を支払わなければなりません。一方、所定休日労働の場合、休日労働ではありませんが、時間外労働をすれば、それに応じた割増賃金を支払わなければなりません。
割増賃金の支払いと計算方法
割増賃金の計算方法は、1時間あたりの賃金に割増率を掛けて算出します。例えば、月給制の場合、基礎賃金を1ヶ月の所定労働時間数で割って時給を算出し、それに割増率を掛けます。
| ① 1 か月の平均所定労働時間=1年間の所定労働日数×1 日の所定労働時間÷12②1時間あたりの賃金=月給÷1 か月の平均所定労働時間③1時間あたりの賃金額 × 時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数×割増率 |
時間外労働と休日労働が重なる場合でも、休日労働の割増率のみが発生します。例えば、休日に9時間労働した場合でも、割増率は35%となり、時間外割増率の25%を加算した60%にはなりません。
他方で、休日労働と深夜労働(22時から5時まで)と重なる場合は、さらに50%の割増賃金が加算されます。
代休を付与する
企業は、休日労働をした労働者に対して代休を付与することを検討します。
労働基準法では、企業には代休を与える義務はありません。そのため、就業規則や雇用契約書に代休に関する規定がなければ、企業は代休を付与しなくても法令に違反しません。
他方で、就業規則や雇用契約に代休に関する定めを置いている場合には、その規定に従って代休を与える必要があります。
労働者が休日出勤を拒否する場合の対応
労働者が休日出勤を拒否した場合、企業は慎重に対応する必要があります。業務上の必要性が高く、労働者の拒否に正当な理由がない場合は、就業規則に基づいて懲戒処分を検討することもあります。
休日出勤の必要性を検討する
休日出勤を命じる前に、その必要性を慎重に検討することが重要です。業務の緊急性や重要性、代替手段、他の人員の有無を精査し、必要な場合にのみ休日出勤を要請すべきです。
従業員の健康や私生活への影響を考慮し、可能な限り平日の業務調整や人員配置の見直しで対応できないか検討しましょう。休日出勤の頻度や対象者の偏りにも注意を払い、特定の従業員に負担が集中しないよう配慮することが大切です。
拒否する理由を聞き取りする
休日出勤を拒否する労働者に対して、拒否の理由を丁寧に聞き取ることが重要です。頭ごなしに拒否する労働者を叱責したり不利益な処分をすることは避けなければなりません。
労働者の個人的な事情や健康上の問題、家庭の事情など、様々な要因が考えられます。例えば、子どもの学校行事や家族の介護、重要な予定などが理由である可能性があります。
聞き取りの際は、労働者が話しやすい環境を整え、威圧的な態度を取らないよう注意しましょう。労働者の立場に立って、休日出勤が困難な状況を理解しようと努めることで、信頼関係を築くことができます。
聞き取った理由が正当なものであれば、代替案を検討することも必要です。他の従業員への業務の振り分けや、出勤日の変更など、柔軟な対応を心がけましょう。一方で、業務上の必要性が高く、他の選択肢がない場合は、その理由を明確に説明し、労働者の理解を得るよう努めることが重要です。
パワハラにならないように注意する
休日出勤を命じる際は、パワーハラスメントにならないよう細心の注意を払う必要があります。
労働者が休日労働を拒否する場合、休日労働命令に従わせたいあまり、威圧的な態度や脅迫的な言動に及ぶことがありますが、このような言動は厳に慎むべきです。
たとえ、労働者が休日労働を拒否する場合でも、企業は休日出勤の必要性を丁寧に説明し、労働者の事情も十分に考慮しながら、双方が納得できる形で調整することが重要です。また、休日出勤を拒否した労働者に対して、不当な処遇や差別的な扱いをすることは避けなければなりません。
懲戒処分を検討する
労働者が休日労働命令に従わない場合には、懲戒処分を下すことも検討しなければなりません。休日労働命令も使用者による業務命令になりますから、業務命令に違反する労働者を懲戒処分に付して、企業秩序を維持させる必要があるからです。
しかし、休日労働命令に従わない一事をもって、安易に懲戒処分とすることは控えましょう。
業務上の必要性と労働者の私生活上の自由を比較して懲戒処分とするかを判断します。例えば、他に代替要員がいる場合、その日に休日労働をしなくても使用者に損害が発生しないような場合には、いくら休日労働命令に従わなかったとしても、懲戒処分とすることは控えるべきでしょう。
仮に、懲戒処分とする場合にも、戒告や譴責といった軽めの処分から始め、命令違反を繰り返し、改善の見込みがなければ普通解雇とすることを検討しましょう。
東洋鋼鈑下松工事事件(最判昭53.11.20)
企業が振り替えた休日に休日労働を命じたところ、
就業規則及び労働協約に,業務の都合上やむを得ない場合において,予め組合と協議して合意が成立したときには休日労働命令又は休日振替ができる旨の規定があり,その旨の労働組合の合意を得て会社が振り替えた振替休日に休日労働を命じたところ,当該命令を歌声祭典準備等を理由に拒んだため,1日の給与の半額を減じる減給処分に付した事案において,「業務命令により法定外休日労働を命じられた労働者は,休日を突然奪われる結果になるが,労働者にとっては,法定外休日であっても,休日について重要な社会的個人的生活利益を有し,例えば,休日の有効利用のため事前に計画をたてて準備をし,一週間の生活設計をたてることもあるのであるから,休日を突然奪われることにより,多大の損失を受け,それが労働者にとり無視し得ない程度に至ることもありうることは,充分考慮されなければならない。」と判示した上,あらかじめ欠勤することを告げていたこと,就業規則には無断欠勤7日で譴責する旨規定されていたこと,企業秩序を混乱させ破壊することを企図していなかったこと,振替休日出勤を拒絶する相当の理由
休日労働の問題は難波みなみ法律事務所へ
休日出勤の強制については、適切なプロセスを踏む必要があります。企業は36協定を締結し、就業規則や雇用契約に基づいて休日出勤を命じる必要があります。一方、労働者は正当な理由がある場合、休日出勤を拒否することができます。
企業は休日労働に対して割増賃金を支払い、代休を付与するなどの対応が求められます。休日出勤を命じる際はパワハラにならないよう注意し、労働者が拒否した場合は応じられない理由を聞き取り、休日労働の必要性を再検討することが重要です。