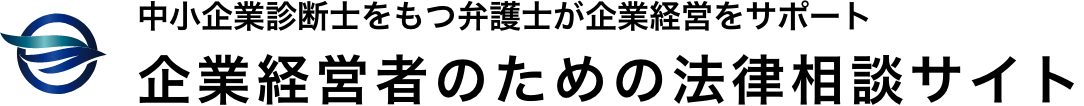問題社員に対して行う懲戒処分の1つに減給処分がある。減給処分とは、その名のとおり、従業員の給与を減額させる懲戒処分です。しかし、減給処分にも一定の制約があります。
本記事では、減給処分にはどのような制約があり、どれ程度まで賃金を減額できるのでしょうか。また処分時には何に注意すべきでしょうか。今回は、減給処分の基本から限度額、注意点を詳しく解説します。
減給処分とは
会社の就業規則や法律に違反する行動をした従業員への懲戒処分の一つが減給処分です。これは、従業員の給与や賞与を減額する処分を意味します。
減給処分は、労働基準法で定められた一定の範囲内で行わなければならず、会社は減給の限度や手続きを十分理解し適切に処置を執る必要があります。
減給処分の限度額
労働基準法では、減給処分に関して具体的な限度額を定めており、これを守らなければ法令に違反する懲戒処分とされます。減給の限度額をしっかりと理解し、公正な人事管理を行うことは企業にとっても非常に重要です。
1回の減給処分は1日分の給与の半額
1回の減給処分においては、労働基準法に基づき、「平均賃金の1日分の半額」を上限とすることが定められています。もしもこの限度を超える減給を実施した場合、労働者から不当な懲戒処分であるとの訴えを起こされる恐れがあります。また、1回の非違行為に対して減給を行う際には、その程度が明確であること、公平性が確保されていることが求められます。この限度額の背景には、労働者の生活の保障と、企業側の懲戒権の乱用を防ぐための考えがあるのです。
1か月の減給の上限は給与の10分の1
減給処分をする場合、1か月の減給の上限が給与の10分の1までに制限されています。
例えば、1か月中に、複数回の問題行為を理由に2回以上の減給処分をする場合、減給額の合計が給与の10分の1を超えて減給処分を行うことはできません。
1か月の給与とは、基本給だけでなく、定期的に支払われる手当ても含む賃金総額を指しています。
平均賃金の計算方法
1回あたりの減給額の上限は、平均賃金の半分です。この平均賃金の計算方法は、労働基準法で定められています。
すなわち、3か月間でその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(労働日数ではない)で割った金額をいいます。
ただし、平均賃金が低い場合には、最低保障額が平均賃金となることがあります。勤務日数が少ないアルバイトやパートタイマーなど、総支給額を総日数で割った金額が最低保障額を下回る場合には、最低保障額が平均賃金となります。
最低保障額は、3か月間の総支給額をその期間の労働日数で割った金額の60%をいいます。
減給処分をする場合には、平均賃金を正しく計算することが求められます。
賞与も減給の対象となる
賞与は賃金の一部とみなされるため、減給の懲戒処分として賞与の減額も可能です。
ただし、ここで注意すべき点は、賞与に対する減給処分も労働基準法91条の適用を受けるということです。すなわち、問題行為1回に対する減給額は平均賃金の1日分の半額を超えてはならず、複数の減給処分をする場合にも1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えることはできません。このようにして、労働者の生活が過度に損なわれないよう、法律による保護が図られているのです。
減給処分をする場合の注意点
会社が従業員に対して減給処分を検討する場合、正当な理由があり、かつ適切な手続きを踏む必要があります。減給処分は従業員の生活に大きな影響を及ぼすものですから、慎重な手続きが求められます。
問題行為の調査を行う
従業員に対する懲戒処分を行う前には、問題行為が実際に起こったかどうかを十分に調査する必要があります。この調査過程で、客観的な証拠や証言を集めることが求められます。証拠が不十分な場合や偏見に基づく決定を行うと、減給処分が無効と判断される可能性があります。
従って、客観的な証拠を収集したり、目撃した社員の聴き取りなど、問題行為の調査を計画的に行うことが大切です。
就業規則で減給処分の定めがあること
減給処分を行うためには、就業規則にその旨の定めが必要です。
就業規則には、どのような行為が処分の対象になるのか(懲戒事由)、懲戒処分の種類やその内容が明記されていることが必要です。
また、就業規則は労働基準監督署への届け出をするだけでなく、その内容を従業員に周知する必要があります。
問題行為に対して減給が重すぎないこと
減給処分を行う際は、その重さが問題行為に見合ったものであることが必要です。たとえ、懲戒事由となる問題行為が認められるとしても、重過ぎる処分は、不当な処分として無効になる恐れがあります。また、過度な処分は、従業員のモチベーションの低下を招く原因にもなりかねません。
そのため、問題行為の悪質さに加えて、同じような過去の事例や本人の反省の有無等を参考にしながら、慎重に処分の程度を検討することが重要です。
就業規則で定めたプロセスを行う
従業員に対して懲戒処分を行う場合には、就業規則で定められたプロセスを遵守する必要があります。就業規則において、賞罰委員会の開催や弁明の機会を与えるなどの手続きが定められている場合、これらを怠ると処分が無効となる可能性があります。公正な手続きを行うことで、従業員の理解を得やすくし、後々のトラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。
減給処分通知書を交付する 減給の懲戒処分通知書の書式・ひな形
減給処分を行う際は、文書で従業員に通知するようにします。
減給の懲戒処分通知書には、処分の理由、減給額、適用する就業規則の条項、効力発生日などの必要事項を記載し、書面にて従業員本人へ正式に交付します。通知書を交付する際には、通知書の写しを取った上で、その写しに受領した旨の署名捺印を社員にしてもらうようにします。
限度額を超えて賃金を減額するための手続き
経営者が減給処分を行う際、従業員に対して労働基準法で定められた上限を超えて減給することはできません。
ただ、減給処分の限度額を超える賃金の減額が認められることもあります。
従業員と合意をする
従業員と合意をして、賃金の減額をする場合があります。
しかし、賃金額は、労働者にとって非常に重要な労働条件であり、賃金の減額は労働者に大きな不利益をもたらします。そのため、従業員との合意による賃金の減額は、従業員の自由な意思に基づくことが必要です。
自由な意思といえるかは、次の事情を踏まえて総合的に判断されます。
- 賃金額の減額の程度や期間
- 説明会や個別面談の実施の有無
- 賃金減額の理由や経緯
- 代償措置の有無
降格処分に伴う減給
賃金減額の1つの形態として降格処分が考えられます。
降格処分とは、職位や役職を下げることで、それに伴って賃金が減少することがあります。降格は人事権の範囲内で行われることもあれば、懲戒処分の一環として行うこともあります。
賃金が、職位や業務に連動して定められている場合、降格処分による職位や業務の変更がされることで、その結果として賃金が減額することがあります。
降格処分による賃金の減額は、減給処分のように1回きりではなく、継続的に行われる点で異なります。また、職位・業務と賃金が連動していない場合には、降格処分をしたとしても、当然に賃金を減額させることはできません。
出勤停止による賃金減額のケース
出勤停止が出された場合も、その停止期間中の賃金は支給されません。
出勤停止は従業員に非違行為があった際に行われる懲戒処分の一形態です。出勤停止処分をするためには、就業規則でその処分内容や期間が明確に定められている必要があります。
出勤停止中、労働者は労働を提供しないため、使用者はその対価である賃金を支払う必要はありません。しかし、出勤停止期間を終え、労働者が出勤を再開すれば従前とおり賃金を支払うことになります。
減給処分をする際には弁護士に相談をすること
給与は労働者の生活を支える重要な労働条件であるため、減給処分を行うと、労働者から強い反発を受けることもよくあります。
従って、減給処分を実施する場合には、慎重な手続きを踏むことが必要です。これは当然ながら、従業員の権利を侵害しないためだけでなく、会社側が労働紛争に巻き込まれるリスクを避けるためでもあります。そこで、減給処分を含む懲戒処分をする際には、弁護士に相談・委任することを検討してください。
労働基準法に沿った減給処分を実施できる
弁護士からの法的なアドバイスを受けることで、減給処分が労働基準法に違反していないかどうかの確認ができます。労基法に違反する減給処分は、無効となるだけでなく、法人としての信頼を損なうリスクにもなり得ます。
弁護士に相談・委任することで、労基法を遵守しながら、適切に問題社員の対応を行うことができます。
減給処分の正当性を判断できる
弁護士に委任することで、減給処分を下すだけの理由や相当性があるかを判断することができます。
専門家である弁護士を通じて、減給処分とする問題行為を客観的に認定できるのか、認定できる場合に、それが就業規則の懲戒事由に該当し、減給処分に値するのかを精査することができます。十分な検討をせずに勢いで減給処分を行うと、会社側には労働紛争に巻き込まれるなどのリスクを招きます。あらかじめ弁護士に相談すれば、会社側が過剰な処分をしてしまった場合の紛争リスクを未然に防ぐことも可能です。
労働紛争の対応を一任できる
減給処分をした後、従業員側から異議が出されたり、労働審判を含めた労働紛争に発展した場合、弁護士が会社側の代理人として、労働者側との折衝や裁判手続きを適切に行います。
従業員との労働紛争は、会社側に多くの負担を生じさせます。対立関係にある従業員との交渉による精神的な負担も招きます。
弁護士に一任すれば、会社の負担を軽減させることができます。